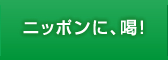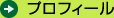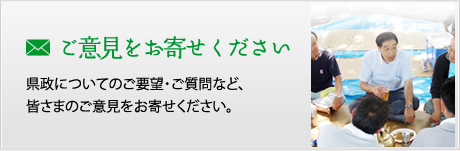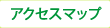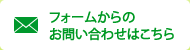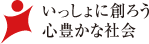今議会最後の一般質問にあたり、一言申し上げます。
本県の人口が毎年一万人減少する時代に入り五年目、今の生活を維持、さらに豊かにしていくには、あらゆる分野で考え方を変え、構造を変えていかなければなりません。その基本は前例踏襲との決別であり、相当な覚悟を持って臨まなければなりません。その思いで、以下質問を致します。
まず、未来に向けたまちづくり・ひとづくりについて伺います。
ご承知の通り、今年は戦後80年の節目の年です。県では富山市長岡にある忠霊塔の整備をはじめ多くの事業に取り組んでこられました。
これまで、国では「戦没者を追悼し平和を祈念する日」を毎年八月十五日として、全国戦没者追悼式を、本県では、富山県戦没者追悼式を行ってきました。
また、各地域・市町村でも行われてきましたが、年々遺族の高齢化により参列者も減少し、県民は戦争があったことさえも忘れ、平和の尊さが希薄になってきていることを強く感じます。
戦争といえば広島、長崎の原爆、沖縄戦がクローズアップされますが富山市では八十年前の八月二日未明、米国のB29爆撃機が50万発以上の焼夷弾を投下し、約11万人が被災し、約三千人もの市民が亡くなり、富山市街地の殆どが焦土と化した事実があります。
しかも地方都市では人口比で最大なのです。 その時の悲惨な話を聴くと、戦争は絶対あってはならないと誰もが思うはずです。
「富山大空襲でどのようなことが起きたのか、事実を伝えよう、語り継ごう」と、今から30年前に「富山大空襲を語り継ぐ会」ができ、これまで活動されてきましたが今は風前の灯火です。
先ほど、藤井議員も質問されましたが、富山大空襲と戦争の事実を知り、平和の尊さを学び続けていくために、県として、富山市と語り継ぐ会などと協議するのはもちろん、
今こそ平和記念館的な拠点施設を整備する必要があると考えますが、
新田知事のご所見をお伺いいたします。
次に、将来の行政サービスのあり方について伺います。
人口減少時代をどう乗り切り、ポジティブに引き継いでいくのか、この課題に対し、昨年、富山県人口未来構想会議を立ち上げ、現状分析、将来の見通し、直ちに取り組むべき施策を示し、令和7年度には、行政部門において、「未来へつなぐ行政サービスのあり方検討会」が設置され、議論されています。
人口減少、少子高齢化、またデジタル技術の進展など、社会経済情勢は大きく変化する中、行政ニーズは、多様化、複雑化に加え、量もどんどん増加してきています。
そのため、行政サービスは、県だけではなく、市町村や民間等も含めた広域的な視点で、県全体を俯瞰し、既存の枠組みにとらわれない思い切った議論が必要であります。
大事なことは、人口データで各地域がどのように変化していくか俯瞰することです。
検討会で、県内人口を1k㎡メッシュで表示された資料はとても分かりやすいものであり、人口が60万人台と推定される2060年までの年齢別や職業別など、あらゆる分野における10年毎のデータを提示し、その姿から取り組むべきことを、バックキャストで考えていくことが重要であります。
検討会の開催期間はもとより、今後10年後、20年後も市町村や事業者、県民が自分事として考えられるよう、データを提供し続け、共有できるシステムにすべきと考えますが、田中経営管理部長に伺います。
さらに、本県ではこれまで教育、医療などあらゆる分野で新川、富山、高岡、砺波ブロックに分けて施策を講じてきたようでありますが、人口減少の中、交通の利便性や、情報通信技術の発達を考えると、もはやブロック単位に分ける必要性がないと考えます。
むしろブロック分けが障害となり、
非効率な面が発生し、県民負担の増に繋がることと、社会経済情勢が大きく変化していることを踏まえ、ブロック単位ではなく、県全体での行政サービスのあるべき姿をイメージする視点が重要と考えます。このことを踏まえ思い切った議論を進めていくべきと考えますが、
知事のご所見をお伺いいたします。
次に疲弊する農村集落についてであります。
農村集落では農業用水路や農地、農道などを維持管理してきたのですが、人口減少により機能しなくなってきている集落が非常に多くなっています。さらに、そこにある祭りや伝統文化も維持できなくなってきています。空家も増えて環境が悪くなるなど、集落機能を維持していくためには、農家以外の方にも住んでもらうことが必要と考えます。又、沿道サービスの目的で造られた施設設が廃業し、空家となっているものも多く見受けられ環境が悪化しています。 家を建てようと思っても、特に市街化調整区域内にある集落は、農地転用のほか、開発行為の許可基準において、農業を営む者、又は分家住宅しか認められていません。 これだけ環境が悪化しているのに、対応できない状況が続いています。
このため、国では平成28年に、既存集落の維持・活性化に繋げるため、市街化調整区域における開発許可の弾力的な運用指針を示しました。それから八年も経過しているにもかかわらず、本県では、この指針の趣旨を踏まえ、他県の状況をみながら、関係市町村と調整し、県の開発審査会で議論を始めたい、との主旨の答弁を毎回繰り返しています。他県の状況よりも、県内の実態を現場に出向くなどして把握に努め、もっと積極的かつスピード感のある対応すべきであります。あらためて、市街化調整区域内の集落の住宅の建築制限について、許可建築物の用途変更を柔軟に認めてはどうか。これまで検討された結果と今後の対応を金谷土木部長に伺います。
次に、農業の人づくりについてであります。
本県の集落営農は農地集積に寄与するとともに、法人化率も増加傾向にあって、農作業の受託から経営そのものを担う形態に移行してきています。
しかし、従事者が1人の割合が約6割、リーダーが、70歳以上が半数以上で高齢化が進んでおり、後継者が確保できない法人が33.5%、非法人では45.1%と非常に高くなっています。
現場ではどうしたらよいのか悩んでいます。一方、農業未来カレッジを卒業した若者が法人経営体で育っています。
独り立ちしたい意欲ある若者もいます。
このような中で、農業経営の相談窓口はありますが、相談に来るのを待つのではなく、後継者不足に悩む集落営農法人などの悩みを出向いて、積極的に聴き、意欲ある若者を募集してスマート農業のステージを提供することにより、生産性の高い農業経営に継承していく必要があります。
そこで、集落営農法人における後継者を確保するため、県と農協が一体となって「プッシュ型」の経営継承支援に取り組むべきと考えますが、津田農林水産部長に伺います。
つぎに、高校再編についてであります。
高校再編については、先月、新時代とやまハイスクール構想実施方針(素案)がまとめられ、県民との意見交換や本議会での議論をふまえ、総合教育会議において実施方針を取りまとめると伺っております。
この素案では、目指すべき学校像、規模が示され、令和20年度までの期間を3期に分けて整備する方針となっています。問題は、今後どのようにして実現していくかであります。
全ての高校が新しい高校づくりを目指すものであることから、今後、大事なのは、全て県教委が決めてから調整するのではなく、各高校で地域事情もふまえ、示された学校像・規模を参考にして自主的に案を出し、纏まったところから順に、新しい高校づくりをするべきと考えますが、廣島教育長の所見を伺います。
次に安全なまちづくりの観点からストーカー事案について伺います。
昨年、被害関係者らが、元交際相手による暴力行為などを警察に繰り返し相談し、つきまとい被害など九回通報したが、警察において適切な対応がなされず、相談女性が殺害されたという痛ましい事件がありました。いわゆる川崎ストーカー事件であります。
遺族から、十分な対応がとられなかったと、訴えられた神奈川県警察本部では、その対応を検証した結果、対処する体制が形骸化し、機能していなかったとし、神奈川県警本部長が、謝罪し、不適切な対応があったことを認めました。
このことを受け、警察庁は、都道府県警察に対処体制の強化などを指示しました。
平成十二年に桶川市の女子大生殺害事件を契機にストーカー規制法が施行されたにもかかわらず、その後も、今回の川崎事件のように最悪のケースも見られることは、非常に残念なことであります。
そこで、ストーカーの相談等の件数が、令和6年中、全国では約二万件と報じられていますが、本県におけるストーカーの相談等の件数の推移と、対処体制の現状、そして、警察庁の指示を受け、どのように対応していくのか、また、体制の強化だけでなく、警察官一人ひとりがストーカー事案に向きあう姿勢が、重要であると考えますが、高木警察本部長の所見を伺います。
次に本県の地域交通と社会資本の整備について伺います。
地域交通を取り巻く環境は、急速な人口減少、少子高齢化、燃料費高騰などにより大きく変化してきていることから、法定計画である「富山県地域交通戦略」が昨年二月に策定されました。令和十年度目標として、県民一人当たりの地域交通利用回数、年五十回など掲げ、
地域交通ネットワークの目指すべき姿の実現に向けて、投資者である県・市町村、参画する地域住民、運行する交通事業者の役割を提示し、ワンチームで取り組むこととされています。
しかし、最近の交通事業者である富山地方鉄道の対応や市町村、地域住民の状況を観ていると、交通戦略の目的が十分理解されていなと感じています。
そこで、改めて、目的と役割についての周知を強化する必要があると考えますが、今後どのように取り組むのか、田中交通政策局長に伺います。
また、富山地方鉄道の経営実態を踏まえ、県、市町村、交通事業者で議論されている最中、「赤字補填ができないのであれば、赤字対象区間を来年廃止する」と脅しとも受け止める発言がされています。
それでは、赤字区間でないところは利便性が確保されているのでしょうか。
地域住民からもっと便利にして欲しいとの要望に対して、殆ど応えてきたように見えません。
住宅街の鉄道駅ホームで利便性を高めるようにするとか、鉄道駅や軌道駅とバスとの連携を図るとか、パークアンドライドをもっと増やすとか、あるいは路線バスルートの見直しなど利便性向上対策のための提案も改善策も殆ど聴いたことがありません。運行会社として相応しいのか疑問であります。
そこで、現在、富山地方鉄道の在り方が検討されていますが、仮に赤字路線を上下分離方式によって存続することになったとしても、富山地方鉄道による運行を前提とせず、他の主体による運行の可能性も含めて検討すべきでないか、交通政策局長に伺います。
次に、地域交通戦略の目標を達成するためには、県民の移動実態を把握し、分析し、対策を講じることが必要と考えます。地域ごとの通勤・通学による移動人口が示されていますが、徒歩、自転車、オートバイ、自家用車、バス、軌道、鉄道などの手段別、年代別などの移動実態が把握されていません。
市町村や地域住民、交通事業者による主体的な取組みを促すためにも、より詳細なデータ、
いわゆる人流データを取得し、オープンデータとして公開し、対策を講じていくことが必要と考えますが、交通政策局長に伺います。
現在、交通政策局では、新幹線、地域交通、空港を中心にそれぞれ縦割りで施策を講じていますが、人流データの活用により、道路の交通量を分析‣可視化するとともに、トラックなどによる物流の状況を踏まえた上で、交通インフラの整備を進めることが効果的と考えられます。
そこで、すべての交通手段を横串で繋いで、利便性の向上を目指す司令塔となる部署、即ち、本県の交通政策をより効果的に実施する体制を整えるため、ハード・ソフト両面で総括する部署を設置すべきと考えますが、蔵堀副知事の所見を伺います。
次に、流杉スマートインターチェンジの改良について伺います。
富山インター出口では、朝夕の混雑時は渋滞し、富山市内に入るのに時間がかかっていることから、渋滞緩和には、利用者を富山インターに加え、富山西インター、流杉スマートインターの3つのインターに分散して富山市内へ入ることが必要であると、提案してきました。
ちなみに、流杉インターは2009年当時は1日2500台でしたが、現在では4100台と利用台数も増えており、一層利便性を増すことが必要であります。
しかし、流杉インターは立地上良い場所にありながら、アクセス道路の整備不足や、12メートルまでの車両しか通行できないこともあり、現状のままでは役割を果たすことができません。特に、物流面では運転手不足からトラックの大型化、ロング化しており、インターを改良すべきと提案してきました。
これに対し、道路を管理する中日本高速道路株式会社や富山市との意向を確認すると、
令和五年二月議会で土木部長から答弁がありましたが、これまでの取り組みと今後どのように取り組んで行くのか、土木部長に伺います。
次に空港問題について伺います。
来年4月から富山空港混合型コンセッションを導入することが決定していますが、札幌便の一時運休、大連便の運休、台北便の長期運休など空港コンセッションが決まる中、本来の空港機能が無くなってしまうのでないか、非常に危機感を覚えています。
ジェイキャストウエイズによる富山空港と関西国際空港と米子空港の就航予定が来年春から秋に延期されたことは残念ですが期待したい。
そこで、今春の臨時便が運行されなかった台北便の運航再開に向けた戦略の見直しをするとともに、国内便については、インバウンド需要が増加していることを好機と捉え、国内主要空港から地方空港に移動した外国観光客が、また主要空港に戻るのではなく、富山空港を拠点とする日本海側にある空港を結ぶルートを開設するとか、中国四国地方空港などへの開設など、富山空港と他の地方空港間を結ぶ新たな国内線の開設に取り組んではどうか、
知事にご所見をお伺いいたします。
次に農業問題についてであります。
本県の農業の労働生産性は全国的に見ても低く、担い手不足の中、生産性向上に向け、スマート農業を推進していくことが重要であります。
そのためには大区画ほ場整備、用水路のパイプライン化、排水路の暗渠化などの基盤整備が不可欠なことから本県では、要望が実に多いのであります。
このことから、農林水産省では、食料・農業・農村基本計画が閣議決定されたことを受けて、令和8年度から農業の構造転換を集中的かつ加速的に進めることとしており、本県もこの動きに
しっかりと対応する必要があります。
そこで、農業の生産性向上に向けてスマート農業を推進していくことが重要であり、大区画ほ場整備等のハード整備とソフト事業との両面から事業を実施していく必要があると考えますが、どのように取り組んで行くのか、知事に所見をお伺いいたします。
国営農地再編整備事業「水橋地区」及び県営事業の実施地区併せて約800haの水橋地域は、米作りを中心に高収益作物を導入した農業経営が望まれており、核となる農業経営体を決めて、伴走支援していく必要があります。
そのため、県では、水橋園芸導入PTと国営水橋ワーキングチームを作り支援されており、課題も見えてきており、課題解決に向けた施策が必要と思っております。
そこで、現在、目標達成に向けどのような課題があり、どのように対処しているのか、事業の進捗状況と併せて、農林水産部長に伺います。
最後に、ほ場整備の施工にあたっては、秋から冬場は雨雪により施工条件が極めて悪くなることから、品質の良い工事が難しく、翌年度への繰り越しが余儀なくされています。
最初から債務負担行為を設定し複数年事業として発注すれば、天候の良い時期の施工計画が立てやすく、農業者に良質なほ場を提供することができます。
そこで、農業農村整備事業の実施にあたっては、十分な工期を確保するため、債務負担行為を積極的に活用すべきと考えますが、農林水産部長に伺いまして、質問を終わります。
ご清聴ありがとうございました。