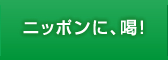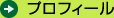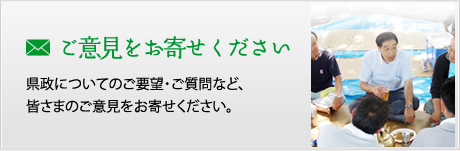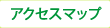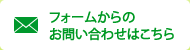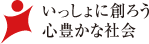本県の人口が毎年1万人減り続けて5年目、2060年には60万人台になると推定されます。こうした中、現状の生活が続けていくには、これまでの仕組みを思い切って変えていかなければなりません。兎に角、以前から言っているように、前例踏襲から決別して、相当の覚悟でもって事にあたらなければなりません。
そのような思いで質問に立ちました。
質問要旨
問1 未来に向けたまちづくり・人づくりについて
(1)富山大空襲と戦争の事実を語り継ぎ、平和の尊さを学び続けるため、富山市や富山大空襲を語り継ぐ会等と協議することはもちろん、今こそ平和記念館的な拠点施設を整備する必要があると考えるが、所見を問う。
(知 事)
(2)将来の行政サービスのあり方検討について
ア 検討にあたっては、人口が各地域でどのように変化していくのかを俯瞰していくことが重要であることから、年齢別や職業別などのあらゆる分野における地域別人口を共有できるようにすべきではないか。
検討会で示された県内人口を1kmメッシュで表示した資料は分かりやすいものであった。人口が60万人台と推定される2060年までの年齢別や職業別などあらゆる分野における10年毎のデータを提示し、その姿から取り組むべきことをバックキャストで考えていくことが重要であり、検討会の開催期間はもとより、今後10年後、20年後も市町村や事業者、県民が自分事として考えられるよう、データを提供し続け、共有できるシステムにすべきと考える。
(経営管理部長)
イ 社会経済情勢が大きく変化していることを踏まえ、ブロック単位ではなく、県全体での行政サービスのあるべき姿をイメージする視点が重要と考えるが、所見を問う。
県は、これまで教育や医療などあらゆる分野で新川、富山、高岡、砺波の各ブロック間のバランスを見ながら施策を講じてきたようであるが、人口減少の中、交通の利便性や情報通信技術の発達を考えると、ブロック単位で分けて考える必要性はない。むしろブロック分けが障害となって非効率な面が発生し、県民負担の増に繋がることから、思い切った考え方で議論を進めてはどうか。
(知 事)
(3)集落機能を維持するためには、農家以外の方にも住んでもらうことが重要であるが、市街地調整区域内の集落では、開発行為の許可基準において、住宅の建築が制限されていることから、許可建築物の用途変更を柔軟に認めてはどうか。
国は平成28年に、既存集落の維持・活性化に繋げるため、市街化調整区域における開発許可の弾力的な運用指針を示しているが、本県ではこの指針の趣旨を踏まえ、他県の状況を見ながら、関係市町村と調整し、県の開発審査会で議論を始めたいとの趣旨の答弁を繰り返し続けている。他県の状況よりも、現場に出向いて県内の実態把握に努め、もっと積極的かつスピード感を持って対応すべき。これまで検討された結果はどうなったのか。
(土木部長)
(4)集落営農法人における後継者を確保するため、県と農協が一体となって「プッシュ型」の経営継承支援に取り組むべきではないか。
農業経営の相談窓口はあるが、相談に来るのを待つのではなく、後継者不足に悩む集落営農法人の悩みを出向いて積極的に聴き、意欲ある若者を募集してスマート農業のステージを提供することにより、生産性の高い農業経営に継承していく必要がある。
(農林水産部長)
(5)「新時代とやまハイスクール構想」実施方針の素案では、目指すべき学校像や規模が示され、令和20年度までの期間を3期に分けて整備する方針となっているが、各学校における検討を終えた学校から新たな高校づくりを開始してはどうか。
全ての高校が新しい高校づくりを目指すものであり、今後大事なのは、県教育委員会が全てを決めてから調整することではなく、各高校で地域事情も踏まえて自主的に案を出すことであり、纏まった学校から順に新しい高校づくりを始めるべき。
(教育長)
(6)本県におけるストーカー事案やその対処体制の現状、そして、警察庁から対処体制を強化するよう指示があったことを受けて、どのように対応していくのか、また、警察官一人ひとりがストーカー事案に向き合う姿勢が重要であると考えるが、所見を問う。
(警察本部長)
問2 本県の地域交通と社会資本の整備について
(1)富山県地域交通戦略について
ア 地域交通ネットワークの目指すべき姿の実現に向けて、県・市町村、参画する地域住民、運行する交通事業者の役割を提示し、ワンチームで取り組むとしており、その周知を強化する必要があると考えるが、どのように取り組んでいくのか。
戦略では令和10年度までの目標として、県民1人当たりの地域交通利用回数を年50回とすることなどを掲げているが、最近の富山地方鉄道や市町村、地域住民の状況を見ていると、交通戦略の目的が十分に理解されていないと感じる。
(交通政策局長)
イ 現在、富山地方鉄道のあり方が検討されているが、仮に赤字路線を上下分離方式によって存続することになったとしても、富山地方鉄道による運行を前提とせず、他の主体による運行の可能性も含めて検討すべきではないか。
富山地方鉄道は「赤字補填できなければ赤字対象区間を来年廃止する」と脅しとも受け止められる発言をしている。また、利便性を高めてほしいとの地域住民からの要望にも応えることはなく、提案や改善案もほとんど聞いたことが無い。こういったこれまでの対応を踏まえると、運行会社として相応しいのか疑問である。
(交通政策局長)
ウ 地域交通戦略の目標達成に向けて、県民の移動実態を把握・分析する必要があることから、人流データを取得し、オープンデータとして公開してはどうか。
地域交通戦略では、地域ごとの通勤・通学による移動人口が示されているが、徒歩、自転車、オートバイ、バス、軌道、鉄道などの手段別や年代別などの移動実態が把握されていない。市町村や地域住民、交通事業者による主体的な取組みを促すためにも、より詳細なデータを公開する必要があるのではないか。
(交通政策局長)
エ 交通政策をより効果的に実施する体制を整えるため、ハード、ソフト両面で総括する部署を設置すべきではないか。
現在の交通政策局では、新幹線、地域交通、空港を中心にそれぞれの縦割りで施策が講じられている。人流データの活用により道路の交通量を分析・可視化するとともに、トラックなどによる物流の状況を踏まえた上で交通インフラの整備を進めることが効果的と考えられることから、全ての交通手段を横串で繋いで、利便性の向上を目指す司令塔となる部署を設置してはどうか。
(蔵堀副知事)
(2)流杉スマートインターチェンジにおいて大型車両が通行できるよう、改良工事を実施すべきと考えるが、これまでの取組みを含め、今後の対応を問う。
富山インター出口で朝夕に発生する混雑を緩和するためには、利用者を富山西インターや流杉スマートインターを含めた3つのインターチェンジに分散する必要があると考えるが、流杉スマートインターはアクセス道路の整備が不十分であり、12メートルまでの車両しか通行できない。令和5年2月定例会で関係団体の意向を確認すると答弁があったが、これまで、どのように取り組んできたのか。
(土木部長)
(3)今春の臨時便が運航されなかった台北便の運航再開に向けた戦略を見直すとともに、インバウンド需要が増加していることを好機と捉え、富山空港と他の地方空港間を結ぶ新たな国内線の開設に取り組んではどうか。
来年4月から富山空港混合型コンセッションを導入することが決定しているが、札幌便の一時運休や大連便の運休、台北便の長期運休など、空港機能が無くなってしまうのではないかと危機感を覚えている。国内の主要空港から地方空港に移動した外国人観光客が、また主要空港に戻るのではなく、富山空港を拠点とする日本海側にある空港を結ぶルートを開設するなど、中国四国地方の空港との路線開設に取り組んではどうか。
(知 事)
(4)農業の生産性向上に向けてスマート農業を推進することが重要であり、大区画ほ場整備等のハード整備とソフト事業との両面から事業を実施していく必要があると考えるが、どのように取り組んでいくのか。
本県では生産性の向上、担い手対策に大区画ほ場整備などの基盤整備の要望が実に多い。食料・農業・農村基本計画が閣議決定されたことを受けて、農林水産省では令和8年度から農業の構造転換を集中的に推し進めることとしており、県もこの動きにしっかり対応する必要がある。
(知 事)
(5)現在実施中の国営農地再編整備事業「水橋地区」について、どのような課題があり、どのように対処しているのか、事業の進捗状況と併せて問う。
国営と県営地区を併せて約800haとなる水橋地域では、米作りを中心に高収益作物を導入した農業経営が望まれており、核となる農業経営体を決めて伴走支援をしていく必要がある。県が設置した水橋園芸導入PTや国営水橋ワーキングチームでは課題も見えてきており、その解決に向けた施策が必要。
(農林水産部長)
(6)農業農村整備事業の実施にあたっては、十分な工期を確保するため、債務負担行為を積極的に活用すべきではないか。
ほ場整備は、秋から冬場は雨雪により施工条件が極めて悪くなるため、品質の良い工事が難しく、翌年度への事業繰越が余儀なくされている。債務負担行為を設定し複数年事業として発注すれば、天候の良い時期の施工計画が立てやすく、農家にも良質なほ場を提供することができる。
(農林水産部長)